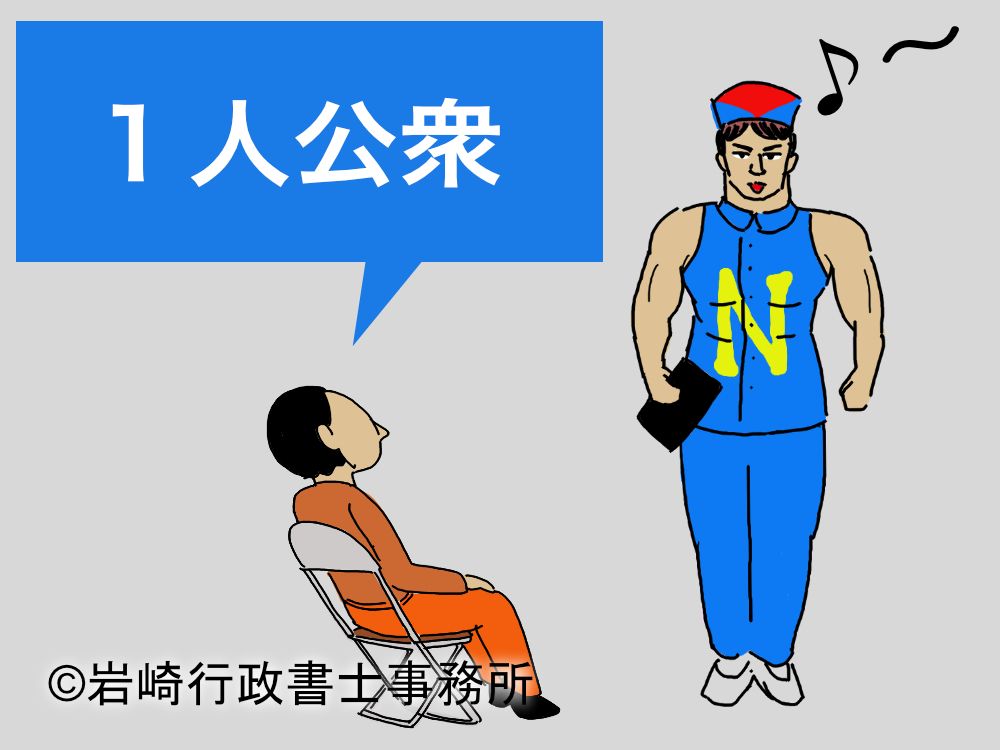上演権及び演奏権の続き
法律上の「公衆」の定義
著作権法上の公衆という表現は、一般的な公衆の概念とは少し異なりますので、それら著作権法で使われる公衆や特定少数等の用語について解説します。
まずは条文です。
(定義)
著作権法第2条5項
この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
条文の解説
イメージ的には不特定多数が公衆となるように思われるかもしれませんが、著作権法の場合は不特定<または>多数となりますので、不特定(多数・少数)と特定かつ多数が公衆に該当します。
- ・不特定多数 ←公衆
- ・不特定少数 ←公衆
- ・特定多数 ←公衆
- ・特定少数
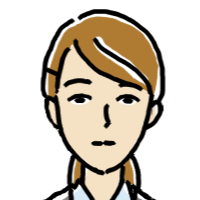
しょみ
不特定多数だけではないのですね。
公衆・特定少数の具体例
「公衆」の例
特定の人(よく知っている人同士)の集まりでも、人数が多ければ公衆として扱われます。
また、不特定の場合は人数にかかわらず公衆として扱われます。
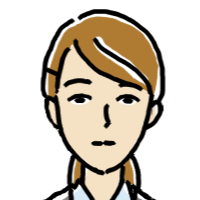
しょみ
一人だけなのに公衆だなんて。

岩崎
その例なら0人でも目的は公衆です。
「公衆」にならない例
一方特定少数の観客に向けて上演・演奏する場合は公衆の定義から外れているため、著作権法第22条の上演・演奏権の対象外となり、著作権者の許可を得ること無く上演・演奏できます。
どのような人が特定の相手に該当するかについて判例では、演奏者と聴き手の間に個人的なつながりがあることが必要であると示されています。
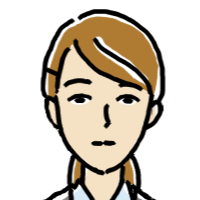
しょみ
個人的なつながりって難しいですね。

岩崎
気心の知れた仲って感じですかね。
営利性について
営利性の要件は?
営利か否かは著作権法第22条に規定が無いため、上演・演奏権の特定少数を満たす場合は、営利であっても著作権が及ばないということになります。
一方で特定は個人的なつながりが必要と示されていることから、営利で特定少数に向けて著作権者の許可を得ずに上演・演奏を行おうとする場合は、演奏者と聴き手の間に個人的なつながりがあることも満たす必要があります。
営利の特定少数はある?
例えば、何度も顔を合わせていて友達同士の関係性があるような少数グループでも、繰り返し参加者を募集し、誰でも加入できる会(例:有料セミナー)であると特定とはいえないなど、営利性が見られる集まりは、結局特定の要件を外れてしまうのかもしれません。
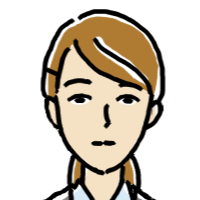
しょみ
音楽教室に関する裁判例がありますね。

岩崎
音楽教室から見て生徒は特定とはいえないとしましたね。
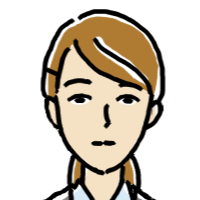
しょみ
営利だからという意味ではないんですよね。

岩崎
生徒募集に応じて誰でも生徒になれるからです。
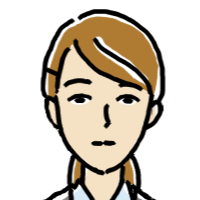
しょみ
個人的なつながりが生まれてもだめですか?

岩崎
レッスン中は募集に応じた不特定の1人ですからね。
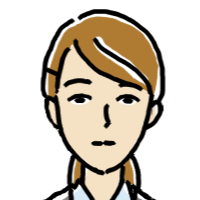
しょみ
先生と生徒の個人的なつながりでの演奏は別ですか?

岩崎
レッスンをはなれて演奏し合うなら特定の相手ですよ。